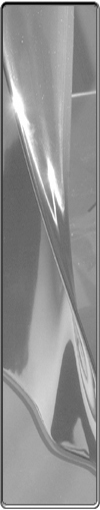|
GLASS AND ART No.23 Autamn 1998
工芸の現在性・各論編1/ロングインタビュー3より抜粋
土岐謙次 ―よどみなき”表面”への眼差し
今年7月、東京のコンテンポラリーアートNIKIで行われた個展で土岐謙次は、素材に 対する一つの新しい試みに取り組んだ。 ―工芸について、漆について、作品の在り方について、彼の語り口が豊かな表情に富む
のは、新しい取り組みに対する手応えのあらわれだろうか。 漆による表現の可能性を、”よどみなき表面 ”という事象を通して追究しようとする、
この若い漆造形作家の情熱を、さまざまな角度から聞いてみた。 取材・構成冨田康子
「漆、工芸、そして歴史」
――土岐さんは非常に明快に、ご自身が漆の作家であると規定して、それを明言され ていますね。
土岐:そうですね、そういうメガネを通して考えるというかね。自分としては、これはあく まで一つの学問で、勝手に自分でテーマを選んで自分で発表していく、一種の学者み
たいなもんやと思っているんです。他の素材の作品を見て「俺やったら、こうつくる な」と思うことは、けっこうあって、やりたいなとは思うんです。でもその場合「木
でこんなんしたらカッコええなあ」とか「こんなん、できるで」というところまでし か思いが至らないんです。趣味でしか終われないし、それ以上踏む込む発想に至れな
い。無責任になってしまいます。でも漆の作品をつくる限りであれば、それについて 何を言われても、すべて受けとめるつもりでいます。それに漆の作品ならね、漆の作
品としてこうつくることで、無駄な歴史をこう排除するぞ、こういう意味で表面 性に 注目するぞ、というのを、自分の趣味じゃなくて、いろんな流れの延長線上で考えら
れる。漆の美術史としての一歩を、俺が刻んでいるぞという実感が伴うんです。
――自分自身を作家だと規定する、いわば“作家意識”みたいなものと、作家として の責任意識みたいなものと、どちらが先ということはないんでしょうけれど、とにか
くその二つがリンクする唯一のフィールドが、今の土岐さんにとっては“漆”である と。
土岐:そう、ある時期ポンと、そういうメガネを通して考えることを決めたんでしょうね。 漆が好きかといわれたら、そりゃ漆のあの、よどみない表面とか好きですよ。でも、
それだけじゃ続かない。ハッキリ言って僕は、作品つくることは仕事やと思ってます し。収入に結びついてるかどうかは別として、ですけどね。
美術をやろうとする人間だったら、過去にしろ現在にしろ、とにかく美術のことにつ いて勉強しますよね。それぞれの作家の仕事にはどういう意味があったのか、文献探
って検証して、そしたらだんだん、その作家なりの真理みたいなものが見えてくるで しょう。美術史の中での位置付けみたいなものも見えてくる。そうすると、この人が
こういう新しい発想で新しい美術観を持ってやったことには、こういう意味があって 、美術史の中に、こういうことを刻んだという一つの真理みたいなものが、いっぱい
見えてくるでしょ。デュシャンも正しい、角偉三郎も正しい、東山魁夷も正しい、皆 それぞれ正しい。そういう真理がたくさん見えてきますよね。それを文化として皆が
受け入れて、美術の世界がだんだん広がってきたと。勉強すればするほど、正しいこ とは広がっていく。でも新たに作家として生まれるために必要最小限の条件というの
は、正しそうに見える真理を一応、納得して認識して、そやけどもそうじゃなくて、 もう一つの新しい真実――少なくとも自分が真実だと信じること――に乗っ取っても
のをつくることだと思います。これは正しいはずやと裏打ちされていることの延長線 上で、それを深めていくのも作家のスタンスの一つかもしれない。でも僕が思うのは、
人に何といわれようと自分がこうだと思った新しいことをやる、そういう有言実行的 な責任感をしょい込むことが、作家と呼ばれる人間には必要だろうということです。
それを押し通せるだけの自分なりの理論づけも含めてね。そういうものがないと、新 たに作家となる必要は、ないだろうと思います。
もちろんそう言ったって、「啖呵切ってしもて取り返しつかへんわ」と思うことは、 たくさんありますよ。でも、それでもやめないつもりで始めてるわけです。さっき、
好きなだけじゃ続かないとか、趣味だけじゃダメだと言ったのは、そういう意味です。
――漆だけでなく「工芸」も、ご自身のテーマであると明言されていますね。「工芸 」に対する関心についても聞かせてください。
土岐:工芸に対する関心というのは、もっぱら「工芸」と言われる現象が、非常に不透明で 不明瞭であることからきています。お互い、こうやって「工芸」ってしゃべってます
けど、認識は非常にズレているはずなんです。 僕は「工芸」って、空間性とか現場性とか、最終的にものが集まって生まれる雰囲気 というか、作品の外部性の集大成のことだと思っています。茶の湯に通
じるような世 界ですね。でも「工芸」という言葉は、そういう意味に即して発達しては、いないで すよね。それはなぜなのか、どうしたら僕が思う「工芸」の意味を取り戻せるかが、
僕にとっては非常に重要です。
――では、そのとき「工芸」というテーマと漆というテーマとを切り結ぶポイントは 何ですか?
土岐:工芸、特に現代工芸といわれる分野は、やきものはやきもの、染織は染織で、それぞ れに独自の発展をし、独自のジャンルになっています。僕のやっている漆も、そうい
う面が強いわけです。でも、もともとの出発点としての「工芸」を意識しているか、 独自の造形ジャンルとしてのそれぞれのジャンルを意識しているかで全然、違ってき
ますよ。 やきものならやきもの、漆なら漆の、その独自の発展部分だけで語れることも、確か に非常に濃い内容だと思うんですよ。先鋭的になっていて、深められていますからね
。ただ、それだけだったら先が細くなっていくばかりじゃないか。特に漆の世界は、 世界中どこでもあるわけではないから、既に先鋭化しているでしょ。でも世界が狭い
だけに、お互いわかり合って許し合っている部分が多いから(これは非常に日本人的 な文化観だと思われますが)、議論が出ない。議論が出ないと、精神が洗練されない。
そのへんは確かに、もどかしいですね。
――そうすると土岐さん自身の漆の作家としての内省的な作業、あるいは自分自身の 仕事に対する自己批評的な作業において、「工芸」という概念の不明瞭さ、不透明さ
が、非常に有効に作用しているわけですね。つまり不明瞭で不透明な概念としての「 工芸」を媒介として、土岐さんという漆作家の内省的な作業が行われているのだ、と。
土岐: 自分のやっていることが、どういう意味をもっているのかという内省的な作業――そ れはネガティブな意味じゃなくて――が、今の工芸の人たちには少ない。あたかもポ
ジティブであるように見える態度が、じつはただ安易に美術のやり方を取り入れてい るだけだったりとか、そういうのは、ものすごく感じますよ。それが僕は問題だなと。
美術の側に踏み込んで、そこで融合を図るというのは、今や非常にポピュラーです。 しかしそれはもはや、形骸化しつつあるように思います。例えば展示の仕方一つにし
ても、それをインスタレーションという人は、たくさんいる。インスタレーションと は何かという問題を、もういいんだというスタンスで安易に踏み越えてしまう工芸関
係の人って、すごく多いでしょう。でも、簡単に美術の側に踏み越えていく借り物的 なやりかたでは、「工芸」の本当の姿は見えてこない。そうかと思うと、作品が小さ
いから今度は台をつくる、「でも台やからどうでもええねん」と言う人がいます。そ れならばブランクーシの作品を見て、どこからどこまでが台なのかという話を議論で
きるか。そういうことを考える余裕がないのは、やっぱり技に埋没している部分が多 いからじゃないかな。技があれば、いい加減な台の上に乗せたって、作品は成立して
いるように見えますからね。そういう点で、作家の責任は、ものすごく大きいと思い ます。 日本の工芸の世界が、「美術」という言葉が成立した明治時代の時点で、非常に特殊
な括られ方をした歴史ということを考えるのならば、それは日本独自のムーブメント であって、それならそれで、ちょっとした逆境から発生するジャパニーズ・オリジナ
ルなスタンスがあるはずやと思うんですよ。 そこにその作品が存在していることに、どんな意味があるのか。百年前にさかのぼっ て、そこから自分までつなげられるのか。作家として負わなければいけないそういう
責任を、技法であるとか、世襲であるとか、公募展の仕組みであるとか、そういうこ とに転嫁してしまって、自分はその責任から逃れてしまう。「これ、陶器のインスタ
レーションです」と。じゃ、そのインスタレーションて何やねん、その責任をどこで 負うのや。そこで、「ひょっとしたら、その陶器のインスタレーションて、すごくオ
リジナルな意味を持っているかもしれないよ」と言ったら、たいていの人は、「いや 、そこまで考えてないです」と言いますよ。オリジナルであることの責任感がない。
そういう教育で、そこそこの人を輩出してしまう大学の在り方にも、僕はすごく問題 を感じます。
「大学と技術教育」
――土岐さんが思う大学の問題点について、聞かせてください。
土岐:ガラスの世界では、スタジオ・グラス・ムーブメントによって、今まで分業でしかで きなかったガラス制作が、個人レベルで作家としてできるようになったと言われてい
ますね。漆も、分業だったのを一つにして、“漆スタジオワーク”にしたのは、大学 の一つの功績やけども、そのセッティングの仕方が非常にまずかったと思います。そ
こで相変わらず、辛気くさいことやらしたっていうのがね。スタジオグラスがうまく いったからって、“漆スタジオワーク・ムーブメント”がうまくいくものでもないよ
うな気がします。そんなことだったら、木地は木地師で塗師は塗師だったという分業 文化としての漆を、僕が逆に取り戻してもいいじゃないかという気持ちさえ、ありま
すね。
――そういえば確かに、今回の新作では、土岐さんは塗りを職人さんに頼んで仕上げ ていますね。そういう手離れのよさは、「工芸」を意識している作家としては、めずらしいのではないですか。
土岐:だから、「そんなことでいいのか」と言われますよ。でも、海外のビエンナーレなん かが典型で、アーティストが現場監督に徹してることなんて、よくあるでしょう。工
芸だって、それでいいんですよ。人に任せるっていうことは、自分でやる以上に苦し いんですよ。だって本当に、ごまかしきかないですからね。「人にやってもらってん
ねん」と言うと、第三者には手抜きみたいに聞こえてしまう。冷静に考えたら、そん なことないですよ。そのへんちょっと掃除しといて、とは違う次元で頼んでるわけで
すから、頼むほうがより洗練された確かな”眼”が要求されます。
――では工芸における大学の中での技術教育の意味について、どう考えていますか。 例えば、さきほど「大学では相変わらず辛気くさいことを教える」というお話があり
ましたが、それはどういうことですか? 分業体制の中でひたすら効率よくつくるた めの技法と、精度のあるものをつくるための高度な技術とを、区別しないで等価に教
えているということでしょうか?
土岐:うーん、それだけじゃないかな。僕らが習うこと、教わってきたことっていうのは、 ある時代の最新テクノロジーを輪切りにした断面なんです。その断面
を、今の時代の 全然、違うところに持ってきて、「これが一番ええねん」と言っているのが大学です 。今のテクノロジー、今の造形を輪切りにした断面と、昔の輪切りの断面
とでは、こ れだけ違う。だとしたら、その違いはどうでもいいのか。新しいのはかたちだけ、そ んなことでいいのか。 例えば僕みたいな作品を、大学で習った乾漆のやり方でつくったら、ものすごく分厚
くなるはずです。でも「こうやったらええがな、胎にカヤ貼って漆で固めてどんどん 重ねて」って。そんなん分厚くて鈍くさい、どこがええねん、と思いますよ。どうし
てその技法が正しいとされてきたのか、その根拠をまったく問わないで引き継いでい ることが問題なんです。 大学の基礎の勉強では、漆で接着剤つくったりもするんです。たしかに接着力は強い
ですよ。でもその強さって、使うものに必要な強さであって、誰も使わないような美 術作品だったら、そこまでの強さは必要ないかもしれない。糊漆だって、開発された
当時は最新技術だっただろうと思います。でも当時の人に、今の猛烈に強力な接着剤 を、「いいのありまっせ」って見せたら、たぶん今の接着剤を使いますよ。だって糊
漆をつくるのって、大変なんですよ。ニチャニチャして汚くなるし、しかも一番、か ぶれる作業なんです。その鈍くさいことに価値を持たせて、大変なことを一生懸命や
る人は偉い人だということにすり変えていく。そういう問題が、いっぱいあるんです。
――でも、そのあたりは難しいですね。技術教育の重要性をまったく省みないわけに もいかないでしょうからね。
土岐:先生と学生が一緒に研究しましょうって感じがなさすぎる点が、問題なんだと思いま す。大学での技術教育も、職人さんにキチッとした技術を教えてもらうシステムにし
て、先生は先生でオリジナルのものをキチッとつくっていればいいんだと思うんです。 でも、先生が一夜漬けで職人の技術を教えているような状況って、あるでしょう。目
は職人の世界を向いていて、職人に迎合して、でもデザインとかかたちがオリジナル ならそれでいいんだというのは、教育として借り物だと思うんですよ。大学の先生が
テクニシャンでないなら、テクニシャンはテクニシャンとして、大学の中にキチンと したポジションを与えて教育に携わってもらうべきで、それなら健全なんです。そし
たら先生は、作家として、美術の中での自分の作品の意味とか、工芸としての自分の 作品の意味とかについて考えることに集中してそれを学生に示せばいいんです。そこ
から先は学生自身が自律していけばいいんですよ。
――でも、「糊漆ってニチャニチャして汚らしくて古くさいように見えるけど、もと をたどれば鎌倉時代、いや、正倉院御物にだって使われているんです」みたいなレト
リックって、あるんじゃないですか? つまり、そうやって技術の文化的正統性を主 張することで、最新のテクノロジーに対抗していく。そうやって「工芸」の独自性、
技術の意味性を辛うじて保っていく。それがいいとは言いませんし、そこが工芸に対 する誤解を招く要因になっている面もあるでしょう。でも逆に、そういうレトリック
を徹底的に引き剥がしたところで、あとに何が残るのだろうという不安はないのです か?
土岐:レトリックなこだわりとか積み重ねだけがいまや工芸の拠り所ではないと思いますね。 今回の新作で協力をお願いしたカーボンファイバーの会社でも同じような話を聞いた
んですが、日本では鉄鋼産業に対する信仰みたいなものがあるらしいですね。タンカ ーは鉄で決まりだ、みたいな神話が崩れない。でも、カーボンは軽いから、それでタ
ンカーつくったら人が押しても動きまっせ、燃料も少なくて済みまっせ、というのが 真相だと。 僕自身、漆と出会ってから、漆で作品をつくるということに非常にリアリティがあっ
たんですよ。それだったら作業の瞬間瞬間にも、リアリティを持ちながらやりたいと 思うでしょう。その中で、最終的に作品に到達するために必要な作業というのは、き
るだけ合理的にやれないかと思うんです。教わったからやる作業というのは、許せな い。今、人のやっていることについて、「そこは破綻してるよ」とか「そこは矛盾し
てるよ」とか、すごく見えてきちゃうんですよね。そういう人の補いみたいな面 も、 僕の作品にはあるんですよ。 じつは僕の卒業制作は、レリーフの作品なんです。それを搬入したときに「えっ、こ
れは看板や」と思って、えらくショックを受けたんです。大学で四年間、美術を勉強 して漆やって、それでできたのは結局、看板やんけと思った時点で、僕の中では、そ
れまで受けてきた美術教育とか、僕の作家意識みたいなもの――僕は大学に入った時 点で、とにかく、俺は作家でやっていくぞと思い込んでましたから――が、破綻した
。そのあと、大怪我をしたこともあって、しばらく作品もつくらないでいた時期があ って、そのとき頼りにしてたのは、古典的ですけど、じつはデカルトの『懐疑論』な
んです。「疑って疑って、疑った末に残るものがある」ということに感激して、そり ゃそうやと。ニュートラルな気持ちでできることを続けながら、すべてを疑ってかか
ろうと。発泡スチロール疑わしい、カヤを貼るのも疑わしい、漆の塗り方も疑わしい 、とにかく疑わしいぞと。そういうことで何とか、一つの破綻から僕なりのプロセス
の誕生に至ったわけです。
――とすれば、最近はどうなんでしょう、制作の動機となるリアリティや問題意識を 、大学教育への問題意識とは別な次元からも見つけているのではないですか?もちろんこれまでは、大学での教育に対する反発意識みたいなところが、制作の推進力と
して有効に作用していた面もあるようですが。
土岐:それはそうですね。大学で習ったことはおかしいということから離れて、もっと深く 、工芸のこととか、いろいろ考えるようになってきています。
さっきも言った通 り、ある時期、古典的ではあるけれどもデカルトの哲学の世界に助 けられたということがあって、哲学の世界には非常に興味があります。頭の中が蘇る
気がしますよね。森本哲郎の『ことばへの旅』というのは僕の愛読書で、哲学が、自 分の生きている時間にどう関わっているのかとか、そのあたり、この本がなかったら
、僕の今の意識はないというくらい影響受けてますね。今、オーギュスタン・ベルグ の日本の空間論を読んでいて、それもいいんですよ。哲学の専門書は難しくて、往々
にして歯が立ちませんけど、平易に書かれた本であれば、書かれている一言一言が、 僕の頭の中で美術のことに結びついていくんです。そうなってくると、文学のこと、
歴史や哲学のことにも興味が波及してきます。僕のやってることは、そういうこと抜 きには考えられない。工芸の世界は、そういうことに無関係なように思いがちですけ
ど、少なくともデュシャンの影響とか、ピカソの影響とか、考えないわけにはいかな いでしょう。ブランクーシでもジャコメッティでも、カルダーでもいいけど、歴史的
に重要な作家だったら、工芸の技術で作品つくっている人だって、影響受けてるはず です。そう考えていくと、やはり工芸だけでは成り立たないです。発表しようと思っ
たら特にそうで、見に来る人は、美術のことだけ考えているわけじゃないですからね。 僕が驚いたのは、作品を発表してみると、いろんな人がいろんなことを言うってこと
です。それですごく大変なことを始めたんだなと気づいたんですよ。美術のことだけ 考えていればええわと思っていたのに、まったくそうじゃないと。例えば車を運転し
ていて、前だけ見てたらいいかって言ったら、違う。周り見とかな危ないがな、みた いなね。各ジャンルがリンクしているってことを実感しました。だからじつは、読書
の量が増えたのは、展覧会するようになってからなんです。そうなってから、あれ、 工芸の世界のここがおかしい、漆の世界のここがおかしいというのが、だんだん見え
てきて、一時期はそうやってアラ探しみたいなことばかりしていました。その穴埋め 的な作業をしなくてはと思っていたんです。でも実は自分なりの工芸論とか、日本の
文化観について独りでしゃべれるようになったのは最近のことなんですよ。
「作品の在り方、語られ方」
――制作にとってというより、発表するという行為にとって、言葉のコミュニケーシ ョンが大事であったというわけですね。
土岐:対話ということの意味がわかってないと、発表していくのはキツイのと違いますか。 対話と討論とは違いますけど、美術について語るときは、基本的には討論じゃなくて
対話でしょう。対話って、相手を認めた上での認識のギブアンドテイクみたいなこと やから、ある程度は自分のことも棚に上げて、美術の話をしましょうと。それはひょ
っとすると平行線かもしれんけど、ひょっとすると新しい可能性が見えてくるかもし れん。 これについては、思い出すことがあるんですよ。学生の時、合評会をやりましょうっ
て提案したことがあったんです。自分の作品はこうだ、そして自分が思っているスタ ンダードに対して、この作品はこういう距離があると、そういう話をして、スタンダ
ードを共有したり議論したりすることがやりたかったんです。それで初めて合評会し たとき、みんな自分の作品について説明するんですよ。「この作品は、こんなことを
考えて、こんな情景を思い浮かべて、こんな気持ちでつくりました。技法はこれこれ です」みたいな。そんなん、それ以上、話のしようがないでしょ。そうじゃなくて、
例えば同じ情景をキャンバスに描き写した誰々さんという作家が過去にもいますと。 その作家が、思い浮かべた情景というのは、あくまでも作家と鑑賞者との間に対話が
生まれる触媒でしかない。必ずしも鑑賞者が受け取ったものと、作家が思い浮かべた ものとは同じとは限らない。でも、そこで対話が成り立つとしたら、その作品にはど
んな意味があるのか。それに、キャンバスに絵を描くより漆でやるほうが何倍も大変 なのに、こんな情景を思ってつくりましたってやっているんなら、作用は漆でなくた
って、一緒や。キャンバスでやっても同じことができるのに、漆でやってることの意 味。そのへんについてはどう思うか。そう言うと、学生は黙ってしまうんですよ。そ
んなことまで考えてない。
――同じ質問を土岐さんが受けたとしたら、どう答えますか?
土岐:僕の場合だったらそれは、オブジェとは何かという話につながってきますね。工芸関 係の人って、オブジェって言葉をすごくよく使いますけど、オブジェって、目的とい
う意味ですよね。つまりオブジェとは、作品そのものが最終到達点であるという考え の中で成り立っているわけです。作品を目の前にして何を語るかと言えば、その作品
の存在そのものについて語る。作品のその向こう、作家が思い浮かべた情景、美術の 思想、彫刻や絵画の思想、そういうことを語るための触媒として存在する作品という
のは、オブジェとは違うと思うんですよ。工芸の世界でオブジェと言った場合、もち ろんその作品が示唆する“何か”も重要ですけど、基本的には、ものそのものの在り
方を問おうとすることだと思うんです。だから「僕の作品から大空に羽ばたく翼を想 像して下さい」とか、「僕はこういう翼が好きなんです」とか、イカロスの時代の翼
への憧れとか、そんなことを言いたくないんです。ここに、この作品があることの意 味を、ものそのもので議論したいんです。つまり、作品に自己言及させたいんですよ
ね。高松次郎が自己言及性ということで作品をつくったのも、作品が作家のイメージ とか美術の思想を示唆する触媒でしかないことへのアンチテーゼだと思います。僕は
工芸の世界というのは、ものそのものの在り方をどう考えるのかということが前提に あって、ものとの関係をいかに取り扱うかで成り立っていると思うんですよ。だ
から、ものを見てくれってつもりでつくっているはずなのに、作家が鑑賞者との対話 の中で、「こんな情景思い浮かべてつくりました」と言うんじゃ、矛盾しているわけ
です。せっかく一生懸命ものをつくったのに、ものが触媒でしかないのは、悔しくな いか。僕は、作品をつくるとき、つくりたい作品のことしか思い浮かべていないし、
見る人が何を想像しようが、それはその人の勝手だと思ってます。もし見る人が、作 品の向こう側に何があるのか、作家は何を思い浮かべて何を写しているのかを考える
ようだったら、僕の作品としては失敗です。僕の考えとしては、それは工芸の作品と して失敗だと思う。絵画や彫刻は、その点ちょっと違っていて、思想とか作家のイメ
ージとかが大事にされてきてますけど、そうではなくて、ものそのものの存在だけを 問題にする世界というのが、美術の中での工芸の位置だと思っているんです。
「純粋な表面としての”漆”」
――そこで作品に対する説明を求めるのも気が引けますけど、作品についての話題に 移りましょうか。浮いているようなものをつくりたい、という観念的に近いような皮
膜構造への志向をお持ちのようですが。
土岐:漆は必ず、漆塗りの何か――漆塗りのお碗とか――なんですよね。でも僕が興味があ るのは“表面”です。“よどみなさ”みたいな、“表面”の曲面への憧れなんですね
。漆の表面て、僕は非常に軽快なもんやと思うんですよ。その“表面 ”だけが、宙に 浮かんでいるとすれば、それはクリーンなものだと思います。そういう思いがあって
、“表面”を何とか漂わせたいと思うんですよ、置いてあるとかじゃなくて。でも“ 表面”だけが存在することは、ありえないから、宿命的に何か中身が必要になってく
るんです。でも、だからと言って中身は何でもええのか。塗料であることは譲れへん 。漆は固められるとか接着できるとか言いますけど、僕にとってそれは漆の属性の一
つでしかない。塗ってなんぼのものだから、塗られるもの―中身―の持つ意味も大きい。つまり、胎の存在というのは、作品の中で非常に大きな問題なんです。胎と
なる素材には、その素材なりの必然性というのがあって、その必然性と、作家がこう したいという気持ちの必然性が重なり合って初めて、その作家なりのものができると
思うんです。発泡材は確かに軽くていい、コンパネはまっすぐでいい―そういうの は、ただのコンビニエントな部分であって、その作品のフォルムの本質的な必然性を
説明していることにはならないんじゃないか。そんなふうに胎の問題を考えていたと きに、飛行機の作り方を思い出したんです。飛行機の翼をつくるときって、角材並べ
て布をピンピンに張ってつくるんです。その表面は、すごくきれいですよ。それを見 たときに、ああこれや、と。削り出したりして手で触ってつくる曲面
というのは、ど うしても物理的に、よどみが出る。表面という事象に対してだけではなくて、概念と してもよどみがある。ものが自然につくりだしたものではない。でも、この飛行機の
翼には、手を下すことを最小限にして最大限の効果が生まれているじゃないかと。
――そこでこれまでは、そのピンピンに張った布をFRPで固めて、漆を塗って作品に していたわけですね。そして、今回の新作では、その布を型にして、カーボンファイ
バーで胎となる形態を取り出し、漆を塗るという試みに取り組まれたと。カーボンフ ァイバーはFRPに較べてはるかに強度があり、薄い形態がつくれる、さらには軽いと
いうということで、確かに今回の新作では、皮膜構造の理想に、より近づいている印 象がありますね。
土岐:もともと僕、カーボンを使いたかったんですよ。漆をやるよりも先に、飛行機とかロ ケットとかでカーボンファイバー使っているのは知っていたので。でも経済的な問題
と、素材に対するアプローチにそこまで自信がなかったということがあって、今まで できなかったんです。FRPを使っているときは、下地作業とか、ものすごく練習した
んです。でも、どうしても厚みが出るし、面も、よどんでいる。エッジも鋭くできな い。FRPはグラスファイバーを手で積層していくから、密度が均一じゃないんです。
それで、厚みだけじゃなく、いろんな問題が多くなるんです。今回、初めてカーボン ファイバーを使ってみて、これまでFRPだったら諦めていたはずのプランが、カーボ
ンだったらできるかもしれないと思えてきて、今はそれが嬉しいです。
――そうすると、ますます表面以外の構成要素、例えば支持体の問題などが気になってきませんか?
土岐:支持体は非常に重要な問題ですね。頭の中でイメージしているときは、漆で塗ったか たち―つまり表面―のことだけ考えているんです。でも作品にするときは、その
ままじゃどうにもならん。作品を存在させるために、重力をどう処理するかという問 題が出てきます。どういう支持をするのかということです。どこまでが自分の作品で
どこまでが台で、どこまでが画廊空間なのかということも同じ問題で、避けて通 れな いハードルみたいなものですね。
――では、表面性以外の他の漆の可能性に興味はないですか。例えば加飾とか。
土岐:うーん、ないですね。
――初期の仕事で、表面にテクスチャーをつけた作品もありましたが・・・?
土岐:表面だけで作品をつくるということが意識できていなかった段階で、何かさびしいな と思ってしまって。まだ作品として、理想に近づけてなかったんでしょうね。それで
テクスチャーに走ってしまった。色も、全部を赤にする度胸はなかったですからね。 でも、2回目の個展で、表面のテクスチャーはいらないと、わかったんです。
――色に関しては赤という一貫した選択がありますよね。テクスチャーとは違う問題 として、この赤という選択があるのでしょうか?
土岐:うーん、黒じゃ重いんですよ。空間に対する僕のイメージも関係しているんですけど ね。例えば視野の中に何も入らない、まったく何もない空間があるとしますね。それ
を“空間ゼロ”の状態と考える。その真っ白な空間に、針金みたいなものがシュッと 立ったとします。そうすると、そこに空間ができるというのが、僕のイメージなんで
す。もちろん何もないとしても、そこには空間が成立しているんが、線があれば、そ の線の外部性として、空間が一つ、成立したと言えると思うんですよ。線ではなく面
であれば、それはよりハッキリします。この話を現実に戻すと、作品を置く空間とい うのは、囲まれた空間、画廊という空間なわけです。それを一旦、ゼロの状態にリセ
ットして、そこに赤ペンでシュッと線を入れて、空間を切り裂く。そこに“切り裂か れた空間”という空間ができる。そういうイメージです。その線が水色だったとした
ら、存在感ないなと思うんです。黄色でもないなと。好みもあるんですけど、でも、 ゼロの空間に注釈つけて、空間にしたぞということするには、イメージとしてやっぱ
り赤なんですよね。
――そうすると、空間の大きさに対する作品の大きさ、数は重要ですね。空間を切り 裂くという意味では、画廊いっぱいに作品があってもダメなわけでしょう。
土岐:そうですね。その意味では、今までは作品の数が多かったなという気もします。ただ 、多いかなとは思いつつ、逆に画廊を作品でいっぱいにすることで、漆の空間にいる
という体験のほうを優先させようという気持ちもありましたね。そういう空間に身を 置く、漆の空気を過剰に充満させるということです。今回は少な目にしたんですよ。
ただ今回、新旧二点の作品を展示したのは、新しいカーボンの仕事と、これまでのFR Pの仕事との圧倒的な違いを見せたいという理由が大きいですけどね。
――なるほど。今回、カーボンファイバーという新しい素材を経験したことで、作品 の単体としての大きさの限界が、土岐さんのイメージの中で、変わるでしょう。それ
に応じて、作品と画廊空間との関係に対するアプローチも、変わってくるでしょうね 。今後の展開を期待したいと思います。どうもありがとうございました。(取材・構
成/冨田康子 八月四・五日、京都にて収録。文責/編集部)
|